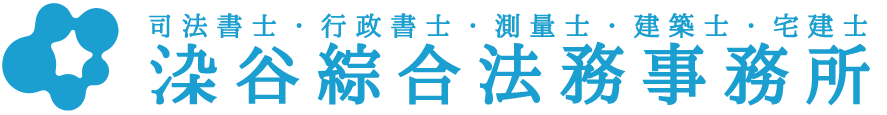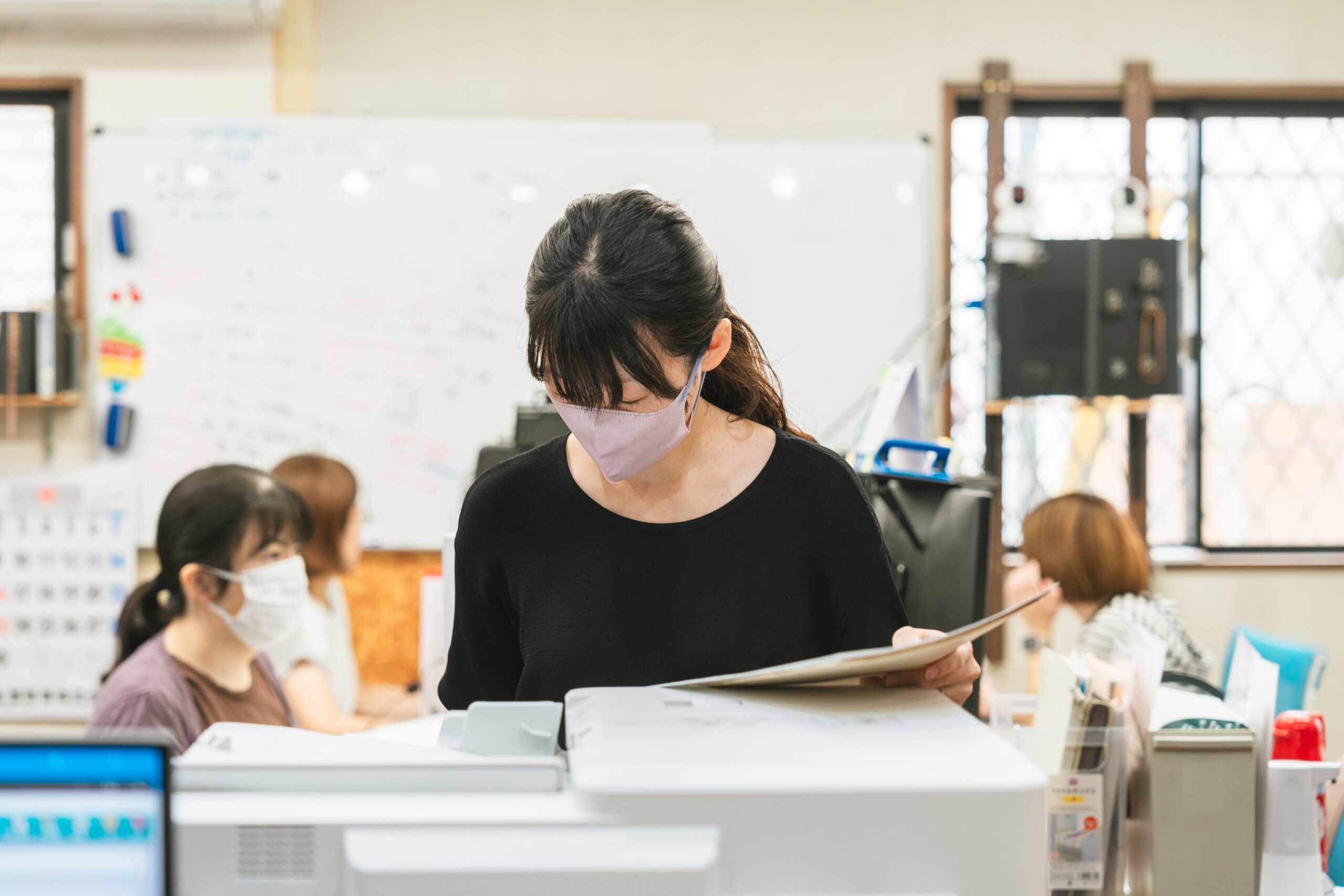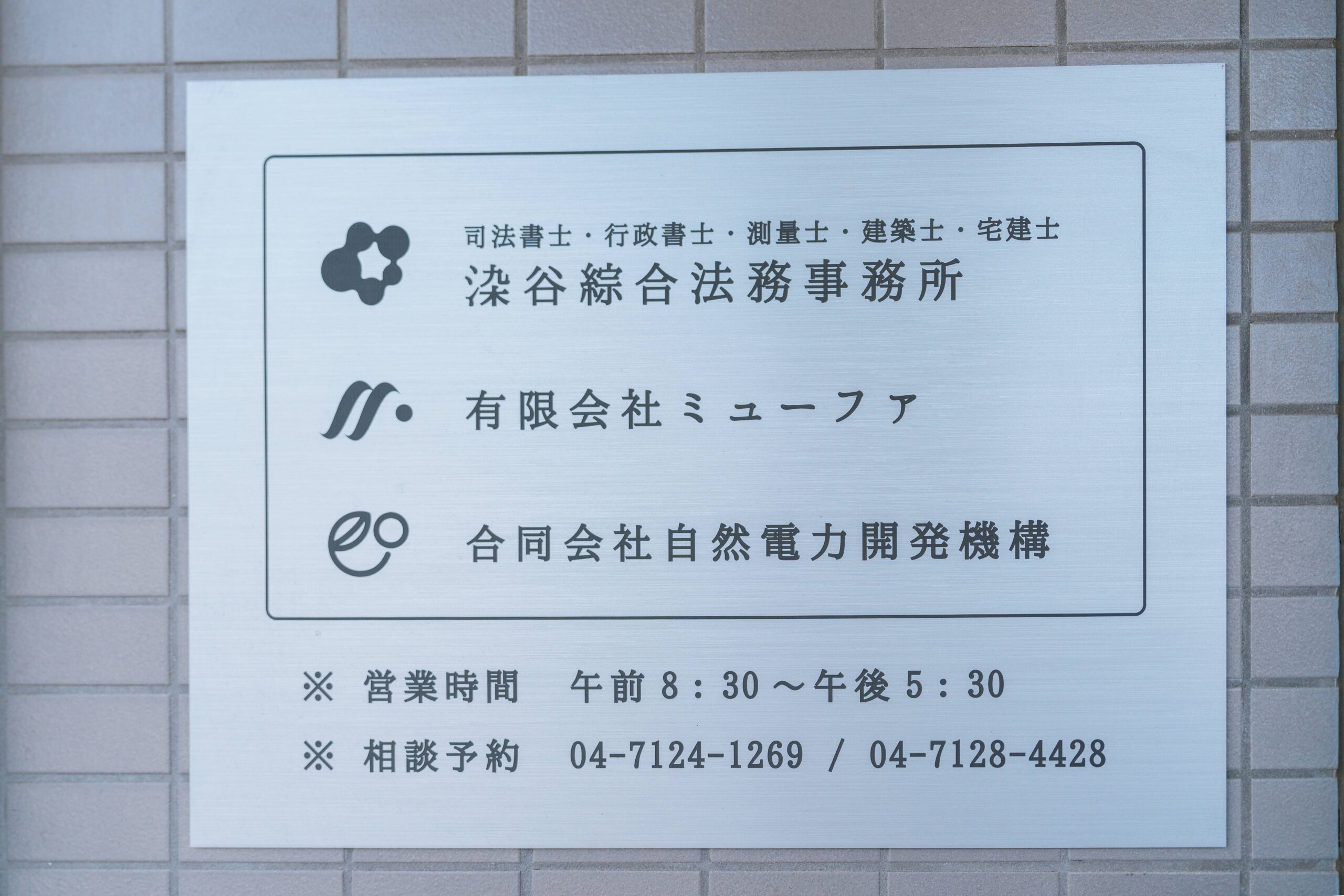相続税申告とは、亡くなった方の遺産に対して相続税がかかる場合に、税務署に申告・納税する手続きです。
すべての人が必要なわけではなく、
遺産の合計額が「基礎控除額」を超えるときに限って申告が必要になります。
◆手続きの流れ
遺産の全体像を把握(不動産、預貯金、有価証券、借金など)
評価額を計算(土地・建物などは評価が必要)
基礎控除をもとに、申告の要否を判断
申告が必要な場合は、税務署へ申告・納税
◆誰がやるの?
相続税申告は、相続人全員で共同して行うものですが、
計算が複雑なため、税理士などの専門家に依頼するケースが多くなっています。
特に次のような場合は、専門家に相談するのがおすすめです:
土地や非上場株など、評価が難しい財産がある
相続人が多数いて、分割が複雑
配偶者控除や小規模宅地の特例などを使いたい
相続税の速算表
相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。 【平成26年12月31日までの場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% - 3,000万円以下 15% 50万円 5,000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 3億円以下 40% 1,700万円 3億円超 50% 4,700万円 【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% - 3,000万円以下 15% 50万円 5,000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 2億円以下 40% 1,700万円 3億円以下 45% 2,700万円 6億円以下 50% 4,200万円 6億円超 55% 7,200万円 この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。 (相法16、平25改正法附則10) 詳しくは弊社提携税理士にお問い合わせください。
●よくある質問
Q:申告の期限は?
A:相続の開始(死亡日)から10か月以内です。
Q:必ず納税が必要ですか?
A:基礎控除額以下であれば、申告も納税も不要です。
ただし、配偶者控除や特例を使いたい場合は申告が必要になることも。
Q:納税方法は?
A:原則として現金一括払いですが、延納や物納が認められる場合もあります。
「税金のこと、正直よくわからない…」という方へ
相続税は、一見「自分には関係ない」と思いがちですが、
不動産を持っていたり、生命保険があったりすると意外と申告が必要になるケースもあります。
当事務所では、相続税に関するご相談から専門家(税理士)との連携まで、
お客様の状況にあわせて丁寧にサポートしています。
「まずは話を聞いてみたい」という方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。